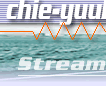| シラウオ |
 |
シラウオ科
学名:Salangichthys (Salangichthys) microdon
分布:北海道〜本州。九州と四国の一部の河川、汽水湖。サハリン〜朝鮮半島。
【解説】
汽水湖や海の沿岸に棲み、産卵期の春、川の河口や汽水湖の浅瀬の水草に卵を産む。有明海には、本種以外にも、近似種のアリアケシラウオとアリアケヒメシラウオも生息する。
棒受網、刺網などのほか、かつて霞ヶ浦等では大きな帆を使った帆曵船(ほびきせん)による漁も行われていた。シラウオ漁は春の風物詩にもなっている。オスはメスよりも臀ビレ付近の体の幅が広い(体高が高い)ので、区別しやすい。
ハゼ科のシロウオと名前も姿もよく似ていて、混同しがちであるが、シラウオは頭部が尖っているが、シロウオは丸く口も大きい。どちらも生きたまま踊り食いするほか、卵とじ、酢の物、天ぷらなどに利用される。
|